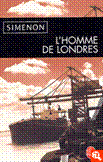|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「倫敦から来た男」 2007年ハンガリー・ドイツ・フランス映画ジョルジョ・シムノンの同名小説を、ハンガリーのタル・ベーラ監督が映画化。 線路と港を見下ろす制御室で働くマロワンは、ある夜、船から降りた二人の男の間で殺人事件が起きたのを目撃し、犯人が去った後、二人が奪い合っていた鞄を海から拾い上げる。中に大量の紙幣を見つけた彼は、それをストーブで乾かし、夜が明けるとなじみのカフェに寄って自宅に戻るが、もう日常はそれまでとは同じには感じられなかった。鞄の行方を探す犯人、そして事件を追ってきた刑事も、マロワンの近くにやってくる。 冒頭から、独特のカメラワークに驚いた。画面一杯に船体が映り、視点が下から上へゆっくりと上がっていくと、甲板で言葉を交わす二人の男が見え、一人がゆっくりと船を降り、線路と反対側の岸辺まで歩くと、もう一人がその足元に鞄を投げ、それから彼もまた、ゆっくりと船を降りて岸辺に向かう。切れ目のない長回し。その場面が太い窓枠の影で何度もさえぎられ、タラップを降りてくる男たちの中から、件の二人を見分けるために目を凝らさねばならない。 それから、ごく手前に男の横顔が映り、場面がその男の観ているものだと分かる。そして、事件が起こるのだが、カメラは主人公のいる場所から離れず、彼の視点で映し続ける。 モノクロの画面。漆黒の海と霧、港から伸びる寂しい線路、制御室の光に白く浮かぶ建物群。そして闇のなかで輝く制御室。侘しく、やりきれない閉塞感が漂っているのに、研ぎ澄ましたような、黒と銀色の動かない画面がものすごく美しかった。 夜の港の風景は何度も大写しで捉えられるのだが、主人公は、道を歩く時も、制御室にいる時と同様、至近距離から背中や顔や上半身に張り付いたようにしか映さない。そのため、昼の町並みはスクリーンの余白にちらちら映るだけ。その一方、主人公が鞄を取りに行く場面では、制御室の塔の足元でカメラが立ち止まり、海から鞄を引き上げるマロワンを遠くからしか見ないし、自宅へ路地を歩くマロワンから距離を置いたカメラに、その後を追う犯人が映り、二人が曲がり角を曲がっても、その後を追わず、延々と細い路地とボール遊びの子どもを映し続ける。自宅で風呂に入った時も、脱ぎ捨てた服とイスのある無人の部屋が、静物画のように長くスクリーンに留まる。マロワンが抱く不安や苛立ちを近くに感じると同時に、何が起こるのか、神経を研ぐような緊張が満ちる映像だった。 事態がどう動いているのかは、カフェでの会話で説明されるのだが、老紳士が犯人にしている説得から、犯人がブラウンという名で劇場の事務所から6万ポンドの金を盗んだこと、被害者はその支配人で、金さえ返してくれば罪を問わず、土曜の夜2週間分の出演料を払うつもりでいる、ということが分かる。その二人からカメラが後ろへずれると、黙ってチェス盤をみつめるマロワンが。次にマロワンが娘を連れて入ってきた時の場面では、犯人が逃げて腕利きの刑事が彼を追っているという話が、声だけ先に聞えてくる。どちらの場面も、全身耳になったマロワンの緊張が伝わってきた。 床掃除で働く娘、それを不満に思うマロワンは無理やり職場から連れ戻し、帰り道で娘に高価な襟巻きを買ってやる。彼の行動を知った妻の絶望の混じった悲しげな表情。大金を隠している不安のせいで、妻と言い合ったばかりなのに、大金が使えると思うことからの行動も、マロワンが家に持ち込むのは、殺伐とした傷だけだ。 娘から小屋に知らない男がいると聞いたマロワンは、食料を持って小屋にでかけるが、中に入った彼をカメラは追わず、戸口をずっと映し続け、一人出てきた彼の姿に、何が起こったのかを悟らせる。マロワンは意外にも鞄を持って自首するのだが、その結果も意外なものだった。 カフェの奥で、犯人の妻が刑事から事情を聞かされ、協力を求められた時、彼女のこわばった顔から涙が流れる、凝視のような長いアップが忘れられない。 原作「L‘Homme de Londre」を読んでみると、映画よりもぐっと賑やかな印象だった。同じく港 また、登場人物も多く、家族には娘の他息子もいるし、妻の兄も顔を出す。転轍手は主人公一人ではなく、仕事場に彼と交代しにやってくる同僚がいる。仕事帰りに寄る居酒屋には、なじみの女カメリアがいて、彼女は殺されたテディの恋人でもあった。ロンドンからは、モリソン刑事のほか、劇場のオーナーのミシェルとその娘エバも金の行方を追ってやって来て、ブラウンの妻を呼び出して協力させるのは、原作ではモリソン刑事ではなく、エバになっている。 原作では息子はバイオリンを習っているし、家は新しく、娘と買い物に出る場面では、彼女は明るい表情を見せて絹の服を着ていて、ぱっとしない生活ながら、映画のような息が詰まるような閉塞感はない。妻と言い争いはするが、口やかましい妻が気難しい夫を辟易させているという風だし、母と娘は何かと相談し合って、ここにあるのは映画の悲壮感とは違う、ごく平凡な日常に見える。 だが、何より大きく違うのは、札束の詰まった鞄を見つけてから、それを返しに行くまでのマロワンの心理が、原作には詳しく語られていることだ。映画では、マロワンは妻と言い争ったりモリソン刑事の質問に答える以外は独り言さえ漏らさず、不安や苛立ち以外の感情は隠されているため、彼が小屋に隠れるブラウンを訪ねる場面も、自首する場面も、非常に唐突な感じを受けた。 原作のマロワンは、自分のことを理解しない妻や、引け目を感じさせる義弟を見返したいという思い、目の前に広がる新しい世界の想像で、手にした金に執着するが、同時に彼の心には犯人への同情が大きくなっていく。街で出くわした時も、恐れを表すのは犯人の方で、犯人がボートに乗って見つかるはずのない鞄を探す場面では、映画と違ってマロワンは不安より相手への哀れみを感じている。気弱そうで、自分と同じ階級の臭いのする男。マロワンが事件の概要を知るのは新聞からだが、無一文で逃げている相手が自分の小屋にいると知ると、彼がいなくなると都合がいいと思うも、その死を願うことはできず、飢えた彼に水が迫るのを気にする。マロワンのなかでは最後まで欲望と良心がせめぎ合うが、ついに犯人と接触した時、相手への共感とは裏腹の結果におののき、逃げることもごまかすこともできたのに、正直に自首するのだ。 さらに、主人公を待つ結末も映画と原作では大きく違う。映画では、結局彼の現実に大きな変化は起こらないが、殺伐とした気分も変わらない。原作では実刑が下り、主人公が見た夢に反して皮肉な結末。だが、心配する妻や娘の姿が温かく、家族の絆が感じられた。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||